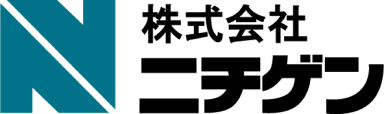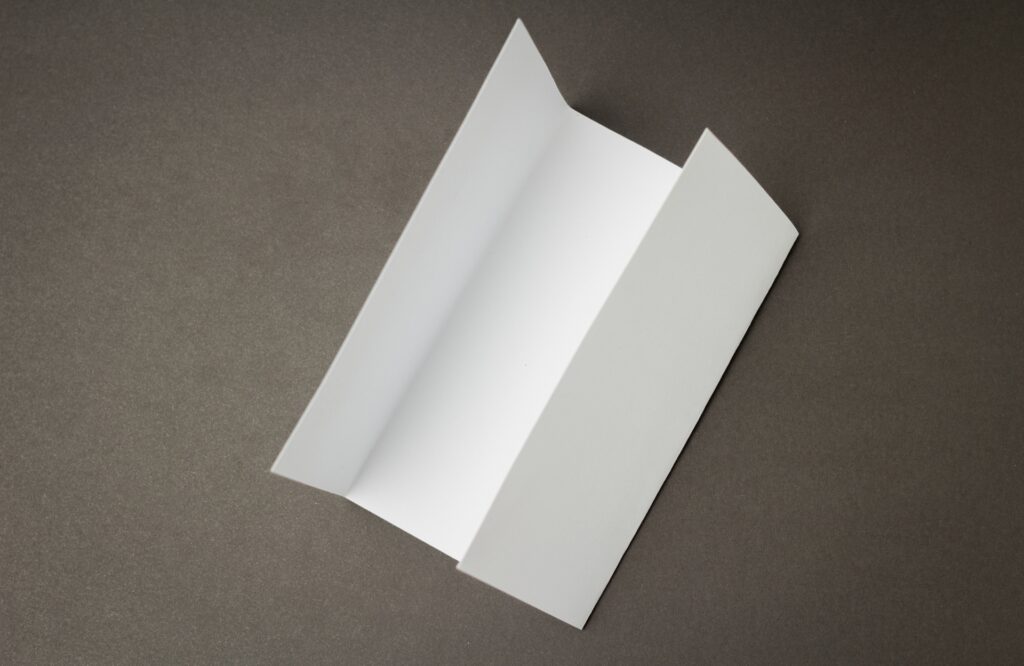パンフレットやチラシの印刷物は、見た目のデザインだけでなく、「どの用紙を選ぶか」でその印象・仕上がり・訴求力が大きく変わります。
たとえば、高級感を出したいブランドパンフレットに安価な紙を使えば、せっかくのデザインも台無しに。
本記事では、「パンフレット印刷における用紙選びの基礎知識」から「用途別おすすめ用紙」「厚みや価格の目安」まで、プロが実務で使う情報を体系的に解説します。
印刷を“任せたい”けど、
どこに頼めばいいかわからない方へ
印刷のことはよくわからないけど、仕上がりには妥協したくない。
そんな方に選ばれているのが、ニチゲンの一貫対応型サービスです。
ご相談・デザイン提案から印刷・納品までをすべて社内で完結。だからこそ、イメージのズレがなく、色味や質感まで思い通りに再現できます。もちろん小ロット印刷にも対応しており、必要なときに、必要な分だけ。
まずはお気軽にご相談ください。
\「これでよかった」と心から思える印刷を提供。/
② パンフレットに使われる印刷用紙の基本知識
コート紙(光沢あり)
パンフレットで写真やカラーを鮮やかに見せたいときには、光沢のある「コート紙」がおすすめです。
なぜなら、コート紙は表面に光沢のある塗料が塗られており、発色がよく、色の再現性に優れているからです。たとえば、旅行会社のパンフレットで美しい風景写真を目立たせたい場合や、商品のイメージを強調したいときに効果的です。
また、インクが紙に染み込まず表面にのるため、細かい文字や写真のディテールもシャープに仕上がります。反面、ツルツルしていて書き込みには向かず、反射で見づらい場合もあります。
つまり、ビジュアル重視のパンフレットや広告用途に最適なのがコート紙です。きれいな写真をしっかり魅せたいときは、ぜひコート紙を選びましょう。
マットコート紙(半光沢)
「上品で落ち着いた印象を与えるパンフレットを作りたい」なら、**マットコート紙(半光沢)**が最適です。
その理由は、マットコート紙はコート紙のような表面コーティングがされていながら、光沢を抑えているため、反射が少なく落ち着いた見た目になるからです。写真は自然なトーンで印刷され、文字も読みやすいので、会社案内や製品カタログなど、情報の信頼性を重視した用途に多く使われます。
また、ペンでの書き込みもしやすく、セミナー資料や説明資料などにも向いています。
つまり、マットコート紙は「見せる」と「伝える」を両立したいパンフレットに向いており、幅広いシーンで使えるバランスの良い用紙です。
上質紙(非塗工紙)
**読み物系や文字が主体のパンフレットには「上質紙」**が適しています。
なぜかというと、上質紙は表面に塗料加工をしていない「非塗工紙」で、手触りが柔らかく、自然な風合いが魅力だからです。光沢がなく、反射がないため、文章を読みやすく、目が疲れにくいのも特長です。
また、ボールペンや鉛筆でもしっかり書き込めるため、申込書やアンケート、記入式の資料にもよく使われます。デザイン面では発色はやや劣りますが、落ち着いた印象を出したい場合に最適です。
つまり、上質紙は「伝える」ことに重点を置いた、ナチュラルで実用的なパンフレット作成に向いている用紙です。
特殊紙(和紙・クラフト紙・ヴァンヌーボなど)
個性や世界観を強く演出したいパンフレットには、特殊紙の活用が効果的です。
理由は、特殊紙は通常の用紙とは異なる素材感や色味、質感を持ち、見る人の記憶に残りやすいからです。たとえば、「和紙」は日本的な雰囲気を演出でき、「クラフト紙」はナチュラルでエコな印象、「ヴァンヌーボ」は高級感と手触りの良さが特徴です。
実際、老舗旅館の案内パンフレットに和紙を使うことで「おもてなし感」が伝わり、エコ商品紹介にクラフト紙を使えば環境意識の高さを演出できます。
つまり、特殊紙はブランドイメージを強く伝えたい時に使うべき、表現力の高い素材です。
用紙の表記ルールと厚み
「kg表記」の意味とは?(例:コート110kg=標準厚)
印刷用紙の「90kg」「110kg」といったkg表記は、紙1000枚の重さを表す印刷業界の単位です。
この単位を知ることで、用紙の厚さ=仕上がりのイメージやコストの感覚がつかみやすくなります。たとえば「コート110kg」は最も標準的な厚みで、パンフレットやチラシに広く使われます。「90kg」はやや薄手、「135kg」はしっかりとした厚みがある印象です。
この数値が上がるほど、紙が厚くなり、重厚感・高級感が増しますが、印刷費用も上がる傾向にあります。
つまり、kg表記は見た目とコストのバランスをとる指標です。用途に合わせたkgを選ぶことが、納得の仕上がりを実現するコツとなります。
90kg/110kg/135kgの違いと使い分け
パンフレットに使われる用紙の厚みは主に「90kg」「110kg」「135kg」が一般的で、それぞれに適した用途があります。
「90kg」は薄手で軽く、チラシや大量配布用パンフレットに向いています。軽いため持ち運びや郵送に便利ですが、やや透け感が出ることがあります。
「110kg」は標準的な厚さで、企業案内や店頭設置パンフレットに最もよく使われます。安定感とコストのバランスが良い厚みです。
「135kg」はしっかりとした厚みがあり、表紙付きパンフレットや高級ブランド向けに適しています。めくりやすく、重厚感のある印象を与えられます。
つまり、紙の厚みは「読みやすさ」「コスト」「印象」のバランスを見て選ぶことが重要です。
ペラ紙と冊子では厚みの選び方が異なる理由
「同じ厚さの紙でも、使い方によって印象が変わる」という点に注意が必要です。
理由は、1枚もの(ペラ紙)と複数ページで綴じる冊子では、紙の重なりやめくりやすさに差が出るからです。
たとえば、135kgの紙を1枚で使うとしっかりした印象になりますが、同じ厚さの紙で24ページの冊子を作ると、厚みが増しすぎて読みにくくなることも。一方、ペラ紙で90kgを使うとペラペラに感じられ、信頼感が下がるケースもあります。
そのため、冊子の場合は110kg程度、ペラ紙では100〜135kgの範囲で調整するのが基本です。
つまり、用途とボリュームに応じて「厚さの最適化」が必要なのです。印象と実用性のバランスを意識しましょう。
用途別に見るおすすめ用紙と活用シーン
- 会社案内(中綴じ・無線綴じ)
- 採用パンフレット(写真映え重視)
- 店舗設置用/展示会用(大量配布向け)
- 高級ブランド・観光ガイド(手触り・高級感重視)
会社案内(中綴じ・無線綴じ)
信頼感のある会社案内を作るには、用紙選びがカギです。
特に企業パンフレットでは「しっかり感」「上質感」が大切なので、中綴じ(ホチキス綴じ)なら110kg程度のマットコート紙、無線綴じ(背を接着する冊子)なら表紙と本文で用紙を分けるのが一般的です。
たとえば、建設業やBtoB企業では落ち着いたマット紙で堅実な印象を与え、ITやベンチャーではツヤのあるコート紙で先進性を演出することもあります。
また、会社案内は文字情報が多いため、反射の少ないマット系の用紙の方が読みやすく、じっくり見てもらいやすい傾向にあります。
つまり、「情報伝達」と「信頼構築」を両立するには、紙の厚み・光沢感・綴じ方まで含めた総合設計が重要です。
採用パンフレット(写真映え重視)
採用パンフレットでは“第一印象”を制すことがカギです。
学生や求職者に好印象を与えるには、写真が鮮やかに映えるコート紙や、上品さのあるマットコート紙を使うことが効果的です。
たとえば、社内風景や社員インタビューなど、ビジュアル重視のページには、発色に優れる「コート紙110kg以上」を使うことで、写真が鮮明に再現され、明るく前向きな印象を与えられます。
一方、落ち着いた業界や真面目な印象を伝えたい場合には、光沢を抑えた「マットコート紙」を選ぶことで、信頼感が高まります。
つまり、採用パンフレットの用紙は「魅せたいイメージ」に合わせて選ぶことで、企業文化を的確に伝える採用ツールになります。
店舗設置用/展示会用(大量配布向け)
大量配布するパンフレットは「軽くて安価で見栄えが良い紙」を選ぶのが鉄則です。
理由は、配布数が多くなると、印刷コストや持ち運びのしやすさが重要になるためです。具体的には、コート紙90kg〜110kg程度が最も一般的で、光沢があり見栄えも良く、コストも抑えやすいというメリットがあります。
例えば、展示会で1,000部を配布する場合、少しでも軽く薄い紙を使うことで、来場者の持ち運び負担も減り、運送コストも削減できます。
ただし、薄すぎると安っぽく見える場合もあるので、最低でも90kg以上の厚さを選ぶのが安心です。
つまり、大量配布用パンフレットでは、コスト・軽さ・印象のバランスを考慮した用紙選びが成果につながります。
高級ブランド・観光ガイド(手触り・高級感重視)
ブランドイメージを高めるパンフレットでは、「紙の質感」こそ最大の武器です。
理由は、高級感や世界観は、デザインだけでなく、「触れた瞬間の感触」からも伝わるからです。
たとえば、ラグジュアリーブランドの案内パンフレットには、上品な手触りの「ヴァンヌーボ紙」や「サテン金藤紙」、または強い光沢でインパクトを出せる「キャストコート紙(ミラーコート)」など、特殊紙・高付加価値紙がよく使われます。
観光ガイドなどでは、「和紙」や「クラフト紙」を使うことで、地域らしさや温かみを表現できます。
つまり、印象的で“記憶に残るパンフレット”を作るには、デザインと紙質の一体設計が必要不可欠です。
カタログの構成別おすすめ用紙
- 10ページ未満(厚めのコート紙/マット紙)
- 10〜50ページ(110kg前後+表紙加工)
- 50ページ超(軽量紙でコスト最適化)
10ページ未満(厚めのコート紙/マット紙)
10ページ未満のパンフレットは「1枚1枚の存在感」が重要です。
なぜなら、ページ数が少ないぶん、紙の薄さが目立ちやすく、全体の印象が「頼りなく」なってしまう可能性があるからです。
そこでおすすめなのが、135kg前後の厚めの用紙(コート紙 or マット紙)。たとえば、A4サイズで4ページの会社案内や製品紹介を作る場合、厚みのある紙にするだけで「しっかりしていて安心感がある」と感じられます。
特に中綴じや折りパンフレットでは、薄紙だと「ヨレやすい」ため、耐久性の面でも厚手が有利です。
つまり、少ページ構成では“紙の厚み=信頼感”。短い構成でも内容を引き立てるには、厚めの用紙が効果的です。
10〜50ページ(110kg前後+表紙加工)
中ボリュームのパンフレットは「本文の扱いやすさ」と「表紙の見栄え」の両立が重要です。
理由は、ページ数が増えるとめくりやすさ・重さのバランスが求められる一方で、表紙で第一印象をつける役割も大きくなるからです。
本文には110kg前後のコート紙またはマット紙が使いやすく、発色や質感、コストのバランスも良好です。
一方で、表紙には「135kg以上」や「PP加工(ラミネート)」などを施し、厚さと保護性を高めることで、耐久性と高級感の両立が可能になります。
たとえば製品カタログやCSRレポートなど、企業の顔として使われるパンフレットにはこの構成が多く採用されます。
つまり、中量ページ構成では、本文と表紙を分けて設計するのがプロの基本です。
50ページ超(軽量紙でコスト最適化)
50ページ以上のカタログや資料集では「軽さとコスト」が紙選びのカギとなります。
なぜなら、ページ数が多いほど用紙の総重量が増し、印刷費・製本コスト・配送料なども膨らむからです。
このような場合は、90kg〜100kg程度の軽量なコート紙や上質紙を使うことで、コストを抑えつつ、扱いやすさを保てます。
たとえば、総合カタログや講習資料、学校案内などでは、軽い紙を使うことで郵送の負担を減らしたり、持ち運びやすくしたりすることが可能です。
また、ページごとの情報密度が高い場合は、発色重視ならコート紙、読みやすさ重視ならマット紙や上質紙と、目的によって使い分けることも大切です。
つまり、大型冊子では**“全体設計”として紙の重さを考えることが成功のポイント**です。
用紙の選び方と印象の違い
仕上がりに与える影響
- 写真・カラー発色が鮮やかなコート紙
- しっとり上品な質感のマットコート紙
- 落ち着きあるナチュラルな上質紙
- ユニークな印象を与える特殊紙
写真・カラー発色が鮮やかなコート紙
鮮やかな写真やカラー表現を求めるなら、コート紙が最適です。
理由は、コート紙の表面が「塗工(とこう)」されており、インクが紙に染み込みにくいため、色がはっきりと乗るからです。たとえば、光沢のある雑誌やフライヤーなどに使われているのがこの用紙で、発色がとても鮮やかで写真が映えるのが特徴です。
特に、製品紹介やサービス案内などでビジュアルの印象が重要な場面では、コート紙が印象強く訴求力を高めてくれます。
一方で、光沢があるぶん反射しやすく、文字主体の資料にはやや不向きな場面もあります。
つまり、“見せる”ことを重視するパンフレットには、発色に優れたコート紙を選ぶことで、情報の伝わりやすさと魅力が大きく向上します。
しっとり上品な質感のマットコート紙
上品で落ち着いた印象を出したいなら、マットコート紙が最適です。
マットコート紙は、表面に薄く塗工がされているものの、コート紙ほどツヤがないため、光の反射が少なく、手触りもしっとりとした高級感のある質感を持っています。
たとえば、金融業・不動産・医療機関など、信頼や安心を重視する業種のパンフレットでよく使われます。写真もきれいに印刷されますが、派手すぎず、全体的に落ち着いたトーンに仕上がるため、「真面目で丁寧な印象」を与えるのに最適です。
また、光が反射しにくいため、文字が読みやすく、長文や情報量の多い構成にも向いています。
つまり、マットコート紙は「静かな上質さ」を伝えたいパンフレットにぴったりな選択肢です。
落ち着きあるナチュラルな上質紙
ナチュラルでやさしい印象を出したいなら、上質紙を選びましょう。
上質紙とは、紙の表面に塗工がされていない「非塗工紙」のことで、コピー用紙と同じようなマットな質感と吸水性が特徴です。インクが少し染み込むため、色味はやや柔らかくなりますが、「自然体」「誠実さ」「温かみ」などの印象を演出できます。
たとえば、CSRレポートや教育系パンフレット、エコ関連の冊子など、「信頼性」や「地に足のついた印象」を大切にする印刷物に使われます。
また、筆記適性も高いため、メモや書き込みが前提の資料にも最適です。
つまり、内容を丁寧に読んでもらいたいパンフレットや、ナチュラルなイメージを打ち出す場面では、上質紙がぴったりです。
ユニークな印象を与える特殊紙
他とは違う印象を残したいなら、特殊紙の選択が効果的です。
特殊紙とは、和紙・クラフト紙・ヴァンヌーボ・エンボス紙など、質感や色、加工の工夫がされた個性的な紙のこと。見るだけでなく「触ったときの驚き」や「記憶に残る感触」があるため、ブランディングに非常に効果的です。
たとえば、地域色を出す観光パンフレットには「和紙」、ナチュラル志向の雑貨店には「クラフト紙」、高級志向のブランドパンフレットには「ヴァンヌーボ紙」などがよく使われます。
もちろんコストはやや高めになりますが、その分、記憶に残るパンフレットとして印象づけることができます。
つまり、「他とは違う何か」を演出したいときは、用紙そのものが強力な個性を発揮してくれます。
表面加工の活用
- ニス加工
- PP加工
- 箔押し
- 型押し など
- 加工×用紙の組み合わせ事例
ニス加工
ツヤや保護効果を軽く加えたいなら、ニス加工がおすすめです。
ニス加工とは、印刷面の上に透明なニスを塗って、ほんのりツヤを出したり、摩擦や汚れから紙面を保護したりする加工のことです。
ラミネート加工よりもコストを抑えつつ、さりげない仕上がりになるため、「ちょっとした高級感」を加えたい場合に適しています。
たとえば、コート紙のパンフレットに部分的なニスを施せば、ロゴや写真だけを引き立てることも可能です(これを「スポットニス」と呼びます)。
つまり、「派手すぎず、印象に残る仕上がりにしたい」場合に、ニス加工はちょうどよい演出ができます。
PP加工(ラミネート)
耐久性と高級感を両立するなら、PP加工が最適です。
PP加工とは、印刷物の表面に「ポリプロピレンフィルム」を貼る加工のことで、水・傷・汚れに強くなるうえ、見た目にも高級感が加わります。
たとえば、何度も手に取られる会社案内や商品カタログなどでは、表紙にPP加工を施すことで、長期間美しい状態を保つことができます。
また、ツヤあり(グロスPP)とツヤなし(マットPP)があり、それぞれで印象が変わるため、デザインと用途に応じた選択が可能です。
つまり、実用性とデザイン性を兼ね備えた表面仕上げとして、PP加工は多くのパンフレットに採用されています。
箔押し
特別感を演出したいなら、箔押し加工が効果的です。
箔押しとは、金・銀・メタリックなどの「箔フィルム」を、熱と圧力で紙に転写する加工のことで、目立たせたいロゴやタイトルに使われる定番技法です。
たとえば、高級レストランのパンフレットや周年記念の会社案内などでは、金箔のロゴがあるだけで「格が違う」印象になります。
また、黒や紺など濃色系の用紙との相性がよく、印刷では表現できない輝きが出せる点も魅力です。
つまり、視覚的に「特別な意味」を伝えたいときには、箔押し加工は非常に効果的な演出手法です。
型押し(エンボス)
紙に“立体感”を与えるなら、型押し加工(エンボス)を検討しましょう。
型押しとは、専用の金型を使って紙に凹凸をつける加工で、ロゴや模様を浮き上がらせることで、触感にも訴えるデザインが可能になります。
たとえば、表紙にエンボス加工された社名があると、光の加減で陰影が出て、見た目にも「こだわり」を感じさせます。
印刷では出せない立体的な表現が可能なため、高級ブランドやデザイン重視のプロモーションツールに多く使われます。
つまり、「触れた瞬間のインパクト」で差をつけるなら、型押し加工は有効な選択肢です。
加工×用紙の組み合わせ事例
仕上がりの印象を最大限高めるには、「紙と加工の組み合わせ」が重要です。
たとえば、マットコート紙+箔押しなら「上品さと華やかさ」が両立でき、クラフト紙+白箔なら「ナチュラルで洗練された印象」になります。
また、ヴァンヌーボ紙+型押しは、印刷と質感の両方にこだわるブランド系パンフレットにぴったり。さらに、**コート紙+ニス加工(部分)**では、ロゴや写真をピンポイントで際立たせることが可能です。
このように、**紙×加工の組み合わせは、デザインの意図をより強く伝えるための「演出装置」**とも言えます。
つまり、ターゲットや用途を見据えながら最適な組み合わせを考えることが、プロフェッショナルな仕上がりへの近道です。
まとめ|パンフレット印刷は用紙選びが重要
パンフレット印刷において、デザインと同じくらい重要なのが「用紙選び」です。
コート紙の鮮やかさ、マット紙の落ち着き、上質紙の読みやすさ、特殊紙の個性──それぞれの特性を理解し、用途に合った紙を選ぶことで、見た目だけでなく“伝わり方”そのものが大きく変わります。また、厚みや加工との組み合わせ次第で、高級感や記憶に残る演出も可能になります。
用紙はただの素材ではなく、パンフレットの「伝達力」を左右する設計要素。目的・ターゲット・予算に応じて、最適な紙と仕上げを選ぶことが、印象に残る一冊をつくるための第一歩です。
「思った通りの印刷に仕上がるか不安…」そんな方へ
「色味が思っていたのと違った…」「仕上がりの質感がチープだった…」
そんな印刷の失敗、もう繰り返さなくて大丈夫です。
ニチゲンでは、一般的な印刷よりも色が鮮やかで高精細な印刷技術に加え、デザインから印刷・製本までを社内で一貫対応。小部数でも、こだわりのある仕上がりを丁寧に実現します。まずは無料でご相談ください。
\仕上がりが不安な方はサンプルも提供/