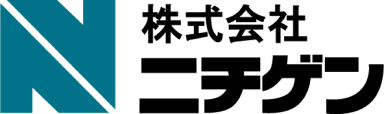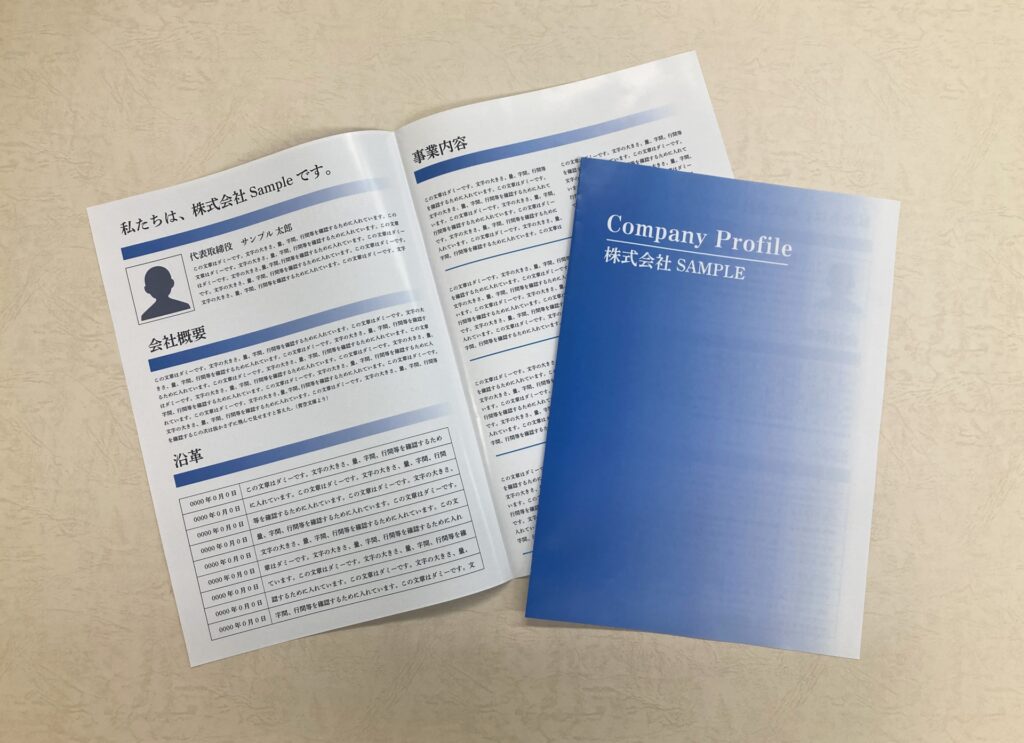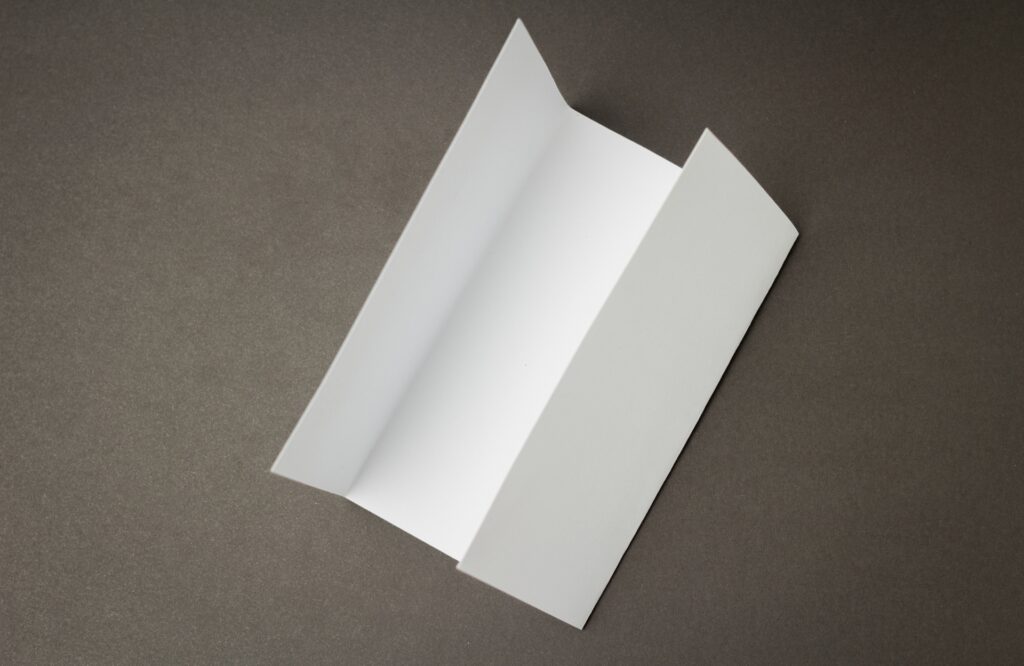デジタル化が進む今でも、会社案内パンフレットは企業の「信頼」や「世界観」を伝える重要なツールです。営業シーンでは商談の第一印象を決め、採用活動では応募者の共感を生み、ブランディングでは企業の姿勢そのものを形にします。
単に「パンフレットを作る」ことが目的ではなく、「何を、誰に、どう伝えるか」こそが印象を左右する本質です。
本記事では、会社案内パンフレットの企画・構成・デザイン・依頼方法までを、初めての方でも理解できるように専門的かつ分かりやすく解説します。読むだけで、自社に合った“伝わる会社案内”の作り方が見えてくるはずです。
印刷を“任せたい”けど、
どこに頼めばいいかわからない方へ
印刷のことはよくわからないけど、仕上がりには妥協したくない。
そんな方に選ばれているのが、ニチゲンの一貫対応型サービスです。
ご相談・デザイン提案から印刷・納品までをすべて社内で完結。だからこそ、イメージのズレがなく、色味や質感まで思い通りに再現できます。もちろん小ロット印刷にも対応しており、必要なときに、必要な分だけ。
まずはお気軽にご相談ください。
\「これでよかった」と心から思える印刷を提供。/
会社案内の役割と種類を理解しよう
- 営業活動用:信頼と商談の入口をつくる
- 採用活動用:共感と応募意欲を喚起する
- PR・ブランディング用:企業の理念や世界観を伝える
- 統合型パンフレット:複数目的を1冊でカバーする万能型
営業活動用:信頼と商談の入口をつくる
営業現場では「会社案内=名刺以上の信頼ツール」です。
多くの企業では初対面の商談や展示会など、まだ取引のない相手に自社を紹介する必要があります。その際、口頭説明やWebサイトだけでなく、手渡せる“会社案内パンフレット”があることで、企業としての信頼感や実績をより具体的に伝えることができます。
たとえば、実績紹介や得意分野、沿革などを整理したパンフレットがあれば、「しっかりした会社だな」「こういう案件を頼めそうだな」と、相手の判断材料になります。逆に、資料が用意されていないと、「まだ準備が整っていない会社かも」と不安を抱かせる要因にもなりかねません。
つまり営業用パンフレットは、「会話の補完」としての役割を果たしつつ、対面後も相手の手元に残り続ける“営業マンの分身”なのです。
営業活動ではパンフレットのデザインや紙質も重要です。表紙の印象やページ構成がしっかりしていると、それだけで“ブランディング”になります。印刷会社と連携し、用途に合った構成・綴じ方・用紙などを選ぶことで、商談をスムーズに進める“信頼の入口”が完成します。
採用活動用:共感と応募意欲を喚起する
採用パンフレットは、会社と応募者の“最初の接点”です。
特に新卒採用などでは、企業の規模や知名度にかかわらず、求職者にとっては「この会社ってどんな雰囲気?働きやすそう?」という印象が重要です。この時、写真やインタビュー、理念などを視覚的に届けられる会社案内は、共感と応募意欲を引き出す大きな武器になります。
たとえば、社員の働く姿やオフィスの様子、キャリアモデルなどが掲載されていれば、「自分もこの中に入れるかも」とリアルに想像できます。一方で、数字や事業内容だけの無機質な内容だと、働くイメージが湧かず、他社に流れてしまうことも。
採用パンフレットの目的は「会社を知ってもらう」ではなく、「ここで働きたい」と思わせること。
そのためには、単なる情報の羅列ではなく、感情に響くストーリー設計や、人の魅力が伝わるビジュアル構成が欠かせません。印刷会社と連携すれば、見開きレイアウトや写真の質感、加工の工夫によって、“心に残る冊子”が実現できます。
PR・ブランディング用:企業の理念や世界観を伝える
会社案内は単なる商品カタログではありません。企業の「価値観」や「哲学」を形にするPRツールでもあります。
特に近年では、消費者・取引先・学生といったあらゆるステークホルダーが「何を作っているか」以上に「どんな想いで作っているか」に関心を持つようになってきました。ブランディング用パンフレットは、その“想い”を紙面で丁寧に伝えるための手段です。
たとえば、歴史ある企業であれば、創業時のストーリーや地域との関わりを丁寧に描くことで信頼と共感が生まれます。逆にスタートアップなら、ビジョンや挑戦の姿勢を前面に出すことで、応援される企業像を打ち出せます。
“理念を見える化”することで、他社との違いが明確になり、ブランドへの愛着が生まれるのです。
また、写真・コピー・紙質・綴じ方まで統一感をもたせることで、「この会社らしいな」という印象が強く残ります。印刷会社との協業によって、ブランド戦略に即した冊子づくりが可能になり、企業の“顔”としてのパンフレットが完成します。
統合型パンフレット:複数目的を1冊でカバーする万能型
営業・採用・PRのすべてを1冊でカバーしたいなら、「統合型パンフレット」が有効です。
特に中小企業や拠点単位での発行において、「営業用も欲しいけど、採用でも使いたい」「会社説明会で配る資料を兼ねたい」というニーズは少なくありません。そんなときは目的別の冊子を複数用意するのではなく、“役割を分けた構成”にすることで対応できます。
たとえば、前半に事業内容と実績、後半に社員紹介やビジョンを配置すれば、営業でも採用でも活用できる構成に。目的別に冊子を分けるよりコスト効率も良く、しかも統一感のあるブランド表現ができます。
統合型の制作では「誰に、どの順で、何を伝えるか」を整理することが重要です。印刷会社に相談することで、ページ配分やデザイン構成も的確にプランニングしてもらえます。
“1冊で多用途に使える”統合型パンフレットは、配布効率だけでなくブランド統一にもつながる、非常に賢い選択肢です。
掲載コンテンツの基本構成参考
- ① 会社概要
- ② 沿革・企業理念
- ③ 代表あいさつ・メッセージ
- ④ サービス/製品紹介
- ⑤ 実績や取引先一覧
- ⑥ 社員紹介・社風・福利厚生
- ⑦ 採用情報・入社フロー
① 会社概要
会社案内の中でまず押さえるべきなのが「会社概要」です。なぜなら、企業の基本情報は、信頼性や透明性の第一歩だからです。会社名・所在地・設立年・代表者名・事業内容などが中心となり、企業の“顔”とも言える部分です。
例えば、どれほど魅力的な製品を紹介しても、所在地や連絡先が不明確では不安を抱かれますよね。会社概要は、企業の名刺のような存在で、閲覧者に安心感を与える要素でもあります。さらに、法人番号や資本金、従業員数などを掲載すれば、対外的な信用にもつながります。
印刷物であれWebであれ、会社案内を制作する際は、この「会社概要」の正確さ・わかりやすさにまず注力することが大切です。
② 沿革・企業理念
**「沿革」と「企業理念」は、会社の“これまで”と“これから”を伝えるために不可欠です。**沿革は会社の歴史を簡潔に年表形式などで紹介するパートで、信頼の蓄積や発展のストーリーを伝えます。たとえば「創業50年」とあれば、それだけで安心感がありますよね。
一方、「企業理念」は“何のために事業をしているのか”という価値観の部分。社員やステークホルダーとの共感や採用活動でも重要です。難しい言葉を使わずに、日々の行動につながる理念が伝わることがポイントです。この2つの情報は、単なる飾りではなく、企業の土台を伝える意味で非常に重要なコンテンツです。
代表あいさつ・メッセージ
**「代表あいさつ」は会社案内の中でも“心”を伝えるページです。**なぜなら、事業の熱意や未来へのビジョンを直接的に表現できるからです。代表の顔写真や手書き風のフォントなどを使うことで、信頼感や人間味がより伝わりやすくなります。
例えば採用活動では、「この人の元で働きたい」と思えるかが応募意欲に影響します。また営業活動でも、代表の姿勢が顧客に安心感を与えることがあります。文章のトーンは堅苦しくなく、あくまで“読者に語りかける”ように。企業の想いが“伝わる言葉”でまとまっているかが、代表メッセージの成功のカギです。
④ サービス/製品紹介
**会社案内で最も読まれるのが「サービス/製品紹介」のページです。**なぜなら、相手にとって「何を提供してくれる会社か」が最も関心のある情報だからです。ここでは、事業領域・強み・他社との違いを簡潔に表現しましょう。
たとえば製造業なら、製品の写真や工程図を交えながら「どのような課題を解決できるか」を示すと効果的です。サービス業であれば、提供価値や顧客の声を入れるのも良いでしょう。このページは“単なるカタログ”ではなく、“価値提案”として構成することが、見込み客や採用希望者の心に響くコツです。
⑤ 実績や取引先一覧
**「実績・取引先」の掲載は、会社案内に“信用力”を与えます。**人は“誰と付き合っているか”で相手を判断する傾向があるからです。これまでの導入企業や業界、プロジェクト名を掲載することで、「うちと同業種でも実績がある」と安心されます。
たとえば「大手メーカーとの取引実績あり」と一言あるだけで、信頼性は大きく高まります。ロゴ掲載や数字での成果紹介も効果的です。ただし、守秘義務や契約上NGのケースもあるため、掲載前の確認は必要です。事例や実績は、第三者の声と同じように“説得力のある証拠”として機能します。
⑥ 社員紹介・社風・福利厚生
**「人」の魅力を伝えるには、社員紹介や社風の紹介が欠かせません。**特に採用パンフレットでは、働く人の表情や声が応募者の不安を解消する大きな要素になります。
たとえば「1日のスケジュール」や「若手社員のリアルボイス」など、リアリティのある情報があると親しみやすくなります。また、社内イベントや福利厚生も紹介することで、会社の雰囲気が伝わります。「〇〇制度あり」「平均残業時間」などのデータも参考になります。
企業文化や職場環境は、働く人の満足度に直結する要素。そこを丁寧に伝えることが、“共感採用”の第一歩になります。
⑦ 採用情報・入社フロー
会社案内で「採用情報」をしっかり伝えることは、応募のハードルを下げるうえでとても重要です。
「何を重視しているのか」「どういった人物を求めているのか」を明示することで、ミスマッチの防止にもつながります。加えて、「選考の流れ(エントリー→面接→内定)」が具体的に書かれていると、安心して応募を検討できます。
よくある「Q&A」形式で、疑問点に答えるのも効果的です。採用ページがあるだけではなく、そこに“安心と期待”が感じられるかどうかが、会社案内としての完成度を高めるポイントになります。
デザイン・仕様の決め方
- ページ数とサイズ(4P/6P/8P、中綴じor二つ折り、ポケットフォルダ等)
- 製本方法(中綴じ、無線綴じ、折り加工)
- 印刷用紙と加工(コート紙・マット・上質紙/PP加工・箔押し)
- 写真・イラスト・図表の活用で情報を伝わりやすく
ページ数とサイズ(4P/6P/8P、中綴じ or 二つ折り、ポケットフォルダ等)
会社案内パンフレットの第一歩は、ページ数とサイズを決めることです。
なぜなら、掲載する情報の量や営業現場での使いやすさに直結するからです。たとえば「4P」はA3二つ折り、「8P」は中綴じ冊子にするのが一般的です。サービス紹介が多ければ「8P」、採用にも使うなら「ポケットフォルダ+差し込み資料」も選択肢になります。サイズもA4が基本ですが、コンパクトなB5やDMサイズなども可能です。
印刷会社に相談することで、情報量と使い方に応じた最適な仕様を選ぶことができ、ムダなく伝わるパンフレットを実現できます。
製本方法(中綴じ、無線綴じ、折り加工)
パンフレットの綴じ方は“使いやすさ”と“印象”を左右する重要な要素です。
中綴じ(針金で中央を留める方法)はページ数が少なくコストも抑えられるため、会社案内やイベント配布物に適しています。一方、無線綴じ(糊で背を固める製本)は厚みがあり、冊子感や重厚感が出るため、製品カタログや報告書などに向いています。また、折り加工のみで冊子にしないスタイル(巻三つ折り・観音折り)も、短いストーリー展開やポスト投函向きに有効です。
綴じ方は“届け方”と“見せ方”のバランスで選ぶべきで、印刷会社と相談することで意図に合ったベストな方法が見つかります。
印刷用紙と加工(コート紙・マット・上質紙/PP加工・箔押し)
用紙と加工の選び方で、会社案内の“印象の質”が大きく変わります。なぜなら、紙の質感や表面加工は、見る人の無意識に影響を与えるからです。
たとえば、ツヤのある「コート紙」は写真の発色がよく高級感が出ます。一方で「マット紙」は落ち着いた風合いで、文字中心の資料や理念重視の案内にぴったりです。「上質紙」は手書き可能でマニュアル等に多く使われます。また、PP加工(表面を薄いフィルムでコーティング)を施すと耐久性が増し、箔押し(金・銀などの光沢装飾)で高級感を演出することもできます。
印刷会社はこうした選択肢を整理し、予算と目的に合った紙と加工を提案してくれる頼れるパートナーです。
写真・イラスト・図表の活用で情報を伝わりやすく
パンフレットでは“ビジュアル”が情報伝達のカギになります。理由は、文字だけでは伝わりにくい内容も、写真や図を使うことで一目で理解できるからです。
たとえば、社内の雰囲気を「言葉」で伝えるより、実際の社員の写真やオフィスの様子を見せた方が、応募者にも親しみが伝わります。また、製品紹介では仕様を表で比較したり、フロー図でサービスの流れを示すことで、見る側が迷わず内容を把握できます。
印刷会社と協力すれば、必要に応じてプロのカメラマンやイラストレーターを手配でき、より伝わるビジュアル設計が可能になります。
よくある課題とその解決法
- 「何を載せるべきかわからない」→業界ごとの参考構成を提示
- 「写真や実績がない」→イラストや理念訴求に切り替える工夫
- 「予算が限られている」→ページ数削減・テンプレート活用で調整
- 「デザインの正解がわからない」→複数案提案で納得の選定が可能
「何を載せるべきかわからない」→業界ごとの参考構成を提示
会社案内をつくる際に「何を載せたらいいのかわからない」という悩みはとても多いです。
この課題を解決するには、まず業界別の「参考構成」を知ることが近道です。
たとえば製造業なら「事業所一覧」「生産体制」などの信頼要素が必要ですし、IT企業であれば「サービス体系図」や「開発フロー」などが効果的です。飲食・サービス業では、写真や接客の雰囲気など“感覚的に伝わる要素”が重要になります。
これは料理でいう「レシピ」に近く、ベースがあると安心してアレンジできます。印刷会社や制作会社に相談すれば、同業他社の事例やテンプレート構成を元に、目的に合った項目を提案してくれます。
「正解がわからない」状態から抜け出すには、自社に合った構成例とともに、目的やターゲットを明確にすることが鍵です。
「写真や実績がない」→イラストや理念訴求に切り替える工夫
写真素材や明確な実績がない企業でも、伝える工夫は十分に可能です。
その代表例が「イラスト活用」や「理念訴求へのフォーカス」です。
写真がない=視覚情報が乏しいということですが、イラストなら柔らかく・親しみやすく情報を補うことができます。たとえば、サービスの流れやスタッフの対応などはイラストで視覚的に表現できますし、抽象的な企業理念も図解すれば理解が進みます。
また、実績がなくても「創業の想い」「社会課題への取り組み」など、“これからの姿勢”を前向きに語ることで、信頼や共感は十分に得られます。
つまり、写真や実績がなくても諦めず、工夫次第で企業の魅力は表現できるのです。
「予算が限られている」→ページ数削減・テンプレート活用で調整
会社案内制作で「コストがかけられない」という声は少なくありません。
しかし、限られた予算でも“伝わるパンフレット”を実現する方法はあります。
代表的なのが、ページ数を抑えた設計やテンプレートの活用です。たとえば4ページ構成にし、裏表紙に地図や会社概要などをまとめれば、費用を削減しつつ情報を網羅できます。また、既存のレイアウトテンプレートをうまく使うことで、デザイン費を抑えつつもプロの仕上がりになります。
さらに、印刷会社によっては「予算に応じた提案」をしてくれるところもあります。事前に予算感を共有することで、コストパフォーマンスの良い制作が可能になるのです。
限られた予算でも、工夫とプロの知見を借りれば十分な仕上がりが得られます。
「デザインの正解がわからない」→複数案提案で納得の選定が可能
「どんなデザインが正しいのか自信がない」という不安は、初めてパンフレットをつくる方によくある悩みです。
しかし、この悩みは“複数のデザイン案を見比べる”ことで解消できます。
デザインは感覚的な要素が大きいため、言葉だけで伝えるのは難しいものです。そこで、初回提案時に「A案:信頼感重視」「B案:スタイリッシュに」「C案:柔らかく親しみやすく」など、方向性の異なる案を提示してもらうと、好みや目的に合ったデザインが明確になります。
このプロセスは、洋服の試着に似ています。“着てみないと似合うかわからない”のと同じで、比較することで納得の選定ができるのです。
正解は1つではなく、「自社にとっての最適解」を見つけることが大切です。
依頼先の選び方と比較ポイント
- 印刷会社:デザイン+印刷の一貫対応が可能
- デザイン会社:ブランディング視点の提案が強み
- 広告代理店:戦略+展開力の高さ
- フリーランス:柔軟対応やコスト重視なら◎
印刷会社:デザイン+印刷の一貫対応が可能
会社案内パンフレットの制作で「効率よく、確実に進めたい」と考えるなら、印刷会社への依頼がおすすめです。
その理由は、デザインから印刷・加工・納品までを一貫して対応できる体制にあります。
例えば「表紙の紙にツヤを出したい」「中綴じか無線綴じか迷っている」といった要望や疑問にも、印刷現場を熟知したスタッフが技術的な観点で的確にアドバイスしてくれます。デザインと印刷が分断されないため、データ不備や色味の違いなどトラブルも起きにくく、スムーズな進行が可能です。
これは、キッチンとホールが一体化したレストランのようなもの。注文から提供までがシームレスで、完成までの質とスピードが安定しています。
特に印刷仕上がりの品質や工程管理を重視するなら、印刷会社に直接依頼する価値は大きいでしょう。
デザイン会社:ブランディング視点の提案が強み
「見た目だけでなく、ブランドイメージまでしっかり反映したい」という場合には、デザイン会社が適しています。
彼らの強みは、ビジュアルだけでなく、企業理念やターゲット像から逆算した提案力にあります。
たとえばロゴの使い方、色彩設計、写真のトーンなどを通じて、「信頼感」や「革新性」といった企業イメージを表現できます。パンフレットは単なる印刷物ではなく、ブランド体験の一部として位置づけられるのです。
これは、服のスタイリストに近い存在。体型やTPOに応じたコーディネートをしてくれるように、企業の個性や目的に合わせて最適なデザインを形にしてくれます。
特に初めてパンフレットを作る企業や、リブランディング中の企業にとっては、デザイン会社の戦略的視点が心強いパートナーになります。
広告代理店:戦略+展開力の高さ
パンフレット単体ではなく、広告・Web・SNSなどと連動させて「全体の販促戦略を強化したい」場合には、広告代理店が適しています。
彼らは印刷物を“単体のツール”としてではなく、“マーケティング戦略の一部”として位置づけて提案してくれます。
たとえば会社案内をベースに、Webサイトや採用動画、展示会ツールなどへ広げる設計も可能。ターゲットごとの訴求ポイントを整理し、伝え方や展開方法までを含めて提案できるのが強みです。
これは、料理でいえば「献立をまとめて考えてくれるシェフ」。パンフレットを主菜としながら、前菜(名刺)、デザート(Web)まで整えてくれる感覚です。
多角的な発信を前提にパンフレットをつくるなら、広告代理店という選択肢は非常に有効です。
フリーランス:柔軟対応やコスト重視なら◎
「小回りが利く制作体制がいい」「予算を抑えたい」という場合には、フリーランスのデザイナーに依頼するのも一つの選択肢です。
特に1人〜数人規模の事業者やスタートアップには相性が良く、柔軟なスケジュール調整や、直接のコミュニケーションがしやすいという利点があります。
また、事務所費用や営業コストがかからない分、同じ予算でも比較的多くの作業に対応してもらえることがあり、コストパフォーマンスが高い傾向にあります。
ただし、印刷工程や専門加工に関しては別の業者と連携する必要があるため、進行管理や品質確認は依頼者自身が主体になることも。
これは「料理を自宅に出張して作ってくれる料理人」のような存在。自由度は高いですが、キッチンや材料の準備も含めて相談が必要です。
意思疎通を大事にしたい方や、小規模案件での機動力を重視する方には最適なパートナーです。
✅ おすすめは「会社案内の制作実績が豊富」かつ「構成提案や印刷加工に詳しい」業者を選ぶこと。
まとめ|“伝わる会社案内”で印象も成果も変わる
「誰に・何を・どう伝えるか」を軸に構成やデザイン、仕様を組み立てることで、営業・採用・ブランディングすべてに活かせる“資産”となります。
その実現には、内容設計から印刷表現まで相談できるパートナーの存在が欠かせません。信頼できる制作会社とともに、自社の魅力を正しく伝える一冊をつくりましょう。
「思った通りの印刷に仕上がるか不安…」そんな方へ
「色味が思っていたのと違った…」「仕上がりの質感がチープだった…」
そんな印刷の失敗、もう繰り返さなくて大丈夫です。
ニチゲンでは、一般的な印刷よりも色が鮮やかで高精細な印刷技術に加え、デザインから印刷・製本までを社内で一貫対応。小部数でも、こだわりのある仕上がりを丁寧に実現します。まずは無料でご相談ください。
\仕上がりが不安な方はサンプルも提供/