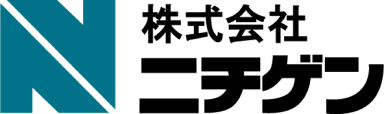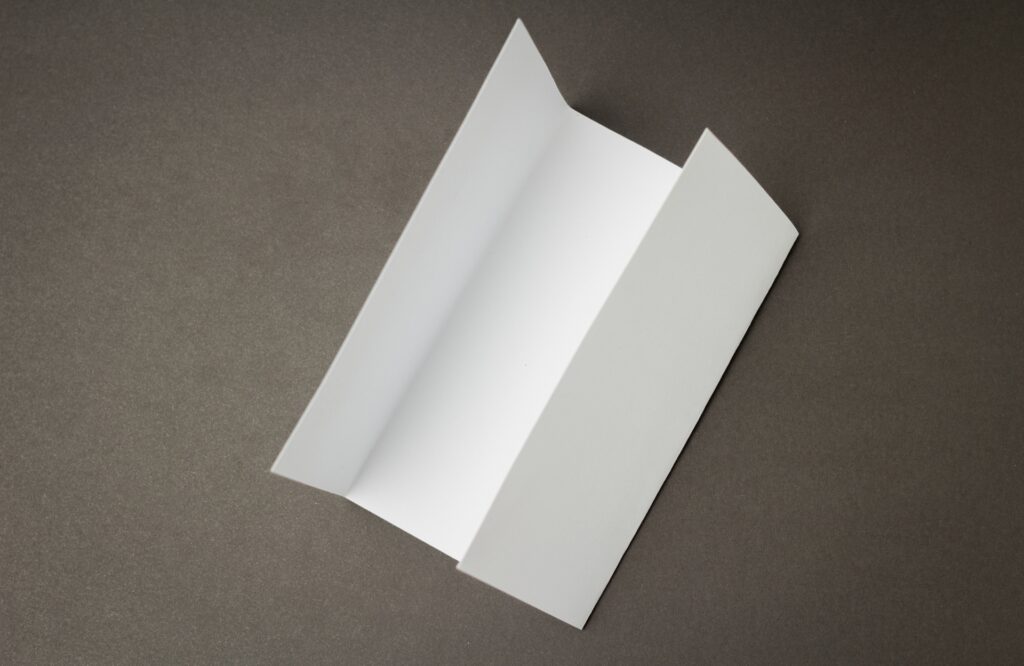会社案内パンフレットは、企業の第一印象を左右する重要なツールです。しかし、「サイズはA4でいいの?」「ページ数は何ページが理想?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。実は、パンフレットの最適なサイズや構成は一律ではありません。「誰に」「何を」「どう伝えるか」という目的によって、適切なサイズや仕様は大きく変わります。
本記事では、A4やA5といった基本サイズの違いから、中綴じ・ポケットフォルダなどの仕様別の特徴、さらに営業・採用・展示会といった活用シーンに応じたサイズの選び方までを、実例を交えてわかりやすく解説します。会社案内をより効果的に活用したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
印刷を“任せたい”けど、
どこに頼めばいいかわからない方へ
印刷のことはよくわからないけど、仕上がりには妥協したくない。
そんな方に選ばれているのが、ニチゲンの一貫対応型サービスです。
ご相談・デザイン提案から印刷・納品までをすべて社内で完結。だからこそ、イメージのズレがなく、色味や質感まで思い通りに再現できます。もちろん小ロット印刷にも対応しており、必要なときに、必要な分だけ。
まずはお気軽にご相談ください。
\「これでよかった」と心から思える印刷を提供。/
会社案内パンフレットの代表的なサイズと特徴
- A4サイズ:王道・標準仕様。信頼感と情報量のバランス◎
- A5/B5サイズ:持ち運びやすく展示会・配布向き
- スクエア型・変形サイズ:ブランディング重視、印象を残したいときに
- サイズ別の比較表(用途・掲載情報・コスト感)
A4サイズ:王道・標準仕様。信頼感と情報量のバランス◎
会社案内パンフレットで最もスタンダードなのがA4サイズです。ビジネス文書として一般的な大きさで、受け取る側にとっても自然で安心感のある印象を与えられます。さらに1ページあたりの情報掲載量が多いため、企業理念、サービス紹介、沿革など多様な情報をバランスよく盛り込むことが可能です。
たとえば、建築業や製造業など、対企業への信頼構築を重視する業種では、しっかりと構成されたA4冊子が活躍します。営業資料や商談ツールとしても、A4クリアファイルに収まりやすく利便性も高いのが魅力です。
「伝えるべき情報が多い」「きちんとした印象を与えたい」場合には、A4が最適な選択肢となります。
A5/B5サイズ:持ち運びやすく展示会・配布向き
コンパクトで配りやすいA5・B5サイズは、展示会やイベントなどでの配布に適しています。かさばらずカバンにも収まりやすいので、受け取る側にとっても負担が少なく、手軽に持ち帰ってもらえる点が特徴です。また印刷コストも比較的抑えやすいため、予算重視の用途にも向いています。
たとえば、住宅リフォーム会社が施工事例を簡潔にまとめたA5冊子を店頭配布するなど、ライトな接点を作りたい場合に重宝されます。
「短く伝えたい」「広く配りたい」シーンでは、A5やB5の選択が効果的です。
スクエア型・変形サイズ:ブランディング重視、印象を残したいときに
印象に残るパンフレットを作りたいなら、スクエア型や変形サイズが効果的です。一般的なA判・B判とは異なる独自のフォルムは、開いた瞬間に「何か違う」と感じてもらえるインパクトを生みます。ブランドの世界観やこだわりを伝えたい企業にとって、サイズ自体がメッセージになることもあります。
たとえば、アパレルブランドが正方形の冊子でルックブックを展開するなど、デザイン性重視の業種での採用が多く見られます。印刷費はやや高めですが、第一印象の強さは抜群です。
「記憶に残るパンフレットを作りたい」なら、変形サイズの選択肢もぜひ視野に入れましょう。
サイズ別の比較例(用途・掲載情報・コスト感)
パンフレットは、用途に合わせてサイズを選ぶことでその効果を最大化できます。たとえば営業で信頼を得たい場面ではA4が適し、持ち帰りやすさを重視するイベントではA5が有効です。一方で、強く印象づけたい場合には変形サイズがブランドイメージの向上に役立ちます。
以下のような視点で選ぶと、より適切な判断ができます:
▼用途別のおすすめ例
営業用:A4冊子
展示会用:A5三つ折り
ブランド訴求:スクエア型
▼コスト感(目安)
A4中綴じ8P:約5~8万円(100部)
A5三つ折り:約3~5万円(100部)
スクエア特殊加工:約10万円以上(100部)
| サイズ | 主な用途 | 掲載情報量 | コスト感 |
|---|---|---|---|
| A4 | 営業・採用 | 多め | 標準〜やや高 |
| A5/B5 | 展示会・配布物 | 少なめ | 低〜中 |
| スクエア/変形 | ブランディング用途 | 中〜高 | 高め |
伝える目的と読み手の状況に応じて、最適なサイズを選ぶことが会社案内の成果に直結します。
ページ数と綴じ方の基本|4P・6P・8Pってどう違う?
- 4ページ(2つ折り):最小構成。初めての会社案内向き
- 6ページ(三つ折り・観音折り):ストーリー展開に◎
- 8P以上(中綴じ冊子):採用・営業など複数目的で情報を整理
- 中綴じと無線綴じの違い、選び方の基準を初心者向けに解説
4ページ(2つ折り):最小構成。初めての会社案内向き
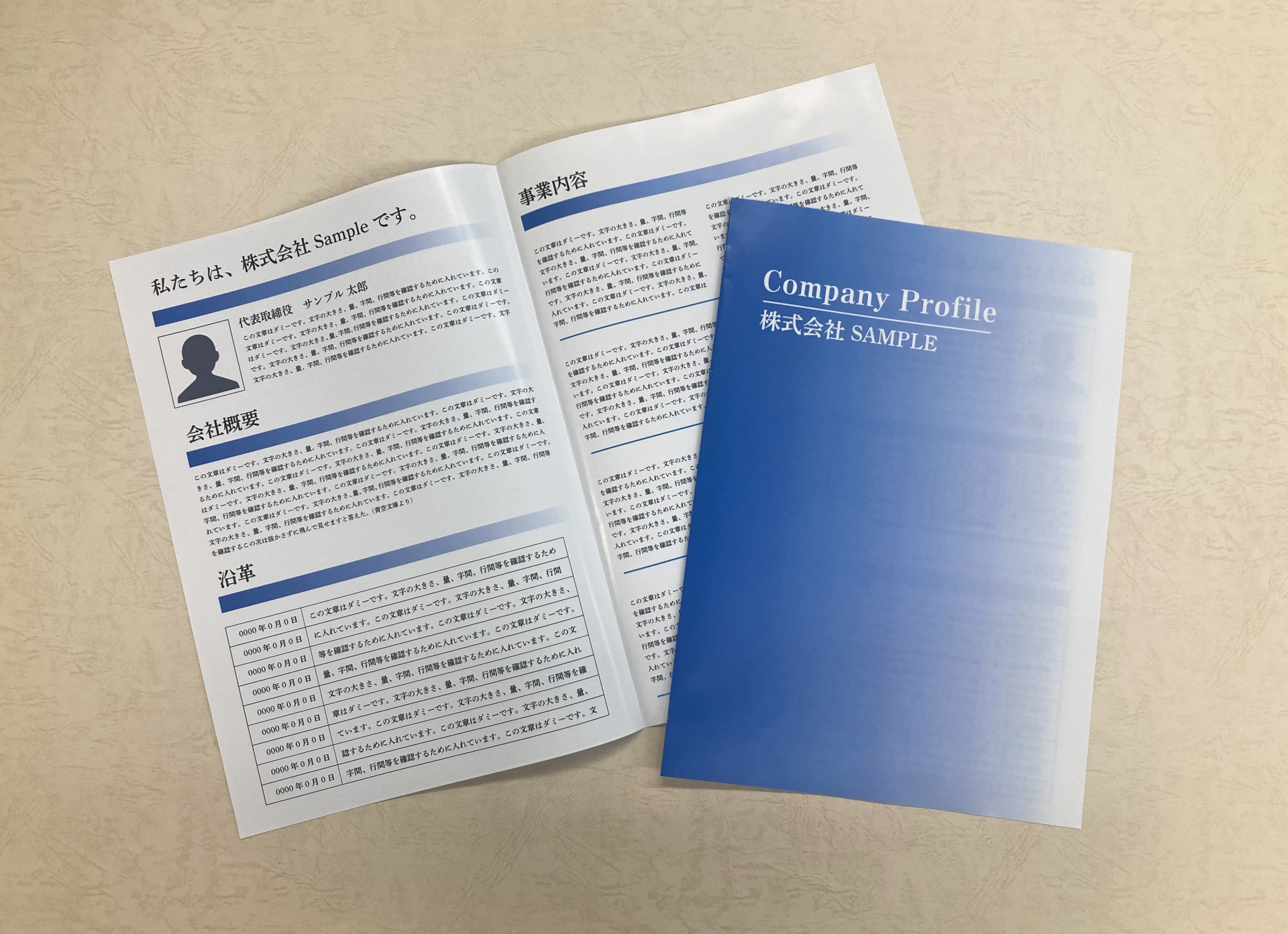
会社案内を初めて作るなら、まずは4ページ構成がおすすめです。
A3サイズの用紙を半分に折るだけでA4仕上がりのシンプルな2つ折りパンフレットが完成し、構成やレイアウトの難易度も低いため、はじめての制作でも安心です。
例えば、会社概要、サービス紹介、代表メッセージ、アクセス情報など、最低限の情報を分かりやすくまとめたい場合に最適です。 飲食店や小規模事業者など、短時間で会社の魅力を伝えたい場面でよく選ばれます。
情報量は限られますが、「まずは名刺代わりの会社案内を」という企業にとっては十分な構成です。
6ページ(三つ折り・観音折り):ストーリー展開に◎【写真事例あり】

※当社の制作実績です。
6ページ構成は「流れで伝える」ことに適したページ数です。
A4三つ折り(巻き三つ折り)や観音折りなどの折り加工で作られるこのタイプは、ストーリー性のある展開が可能です。
例えば、「会社の歴史 → サービス内容 → お客様の声」という順にページを開いていけば、読む人が自然と会社の魅力を理解できる導線が作れます。 展示会や営業配布にも使われやすく、「手に取って、パラパラ読む」場面にぴったりです。
「ストーリー性を大切にしたい」「サービスの流れをわかりやすく見せたい」という企業には、6ページ構成が効果的です。
8P以上(中綴じ冊子):採用・営業など複数目的で情報を整理【写真事例あり】
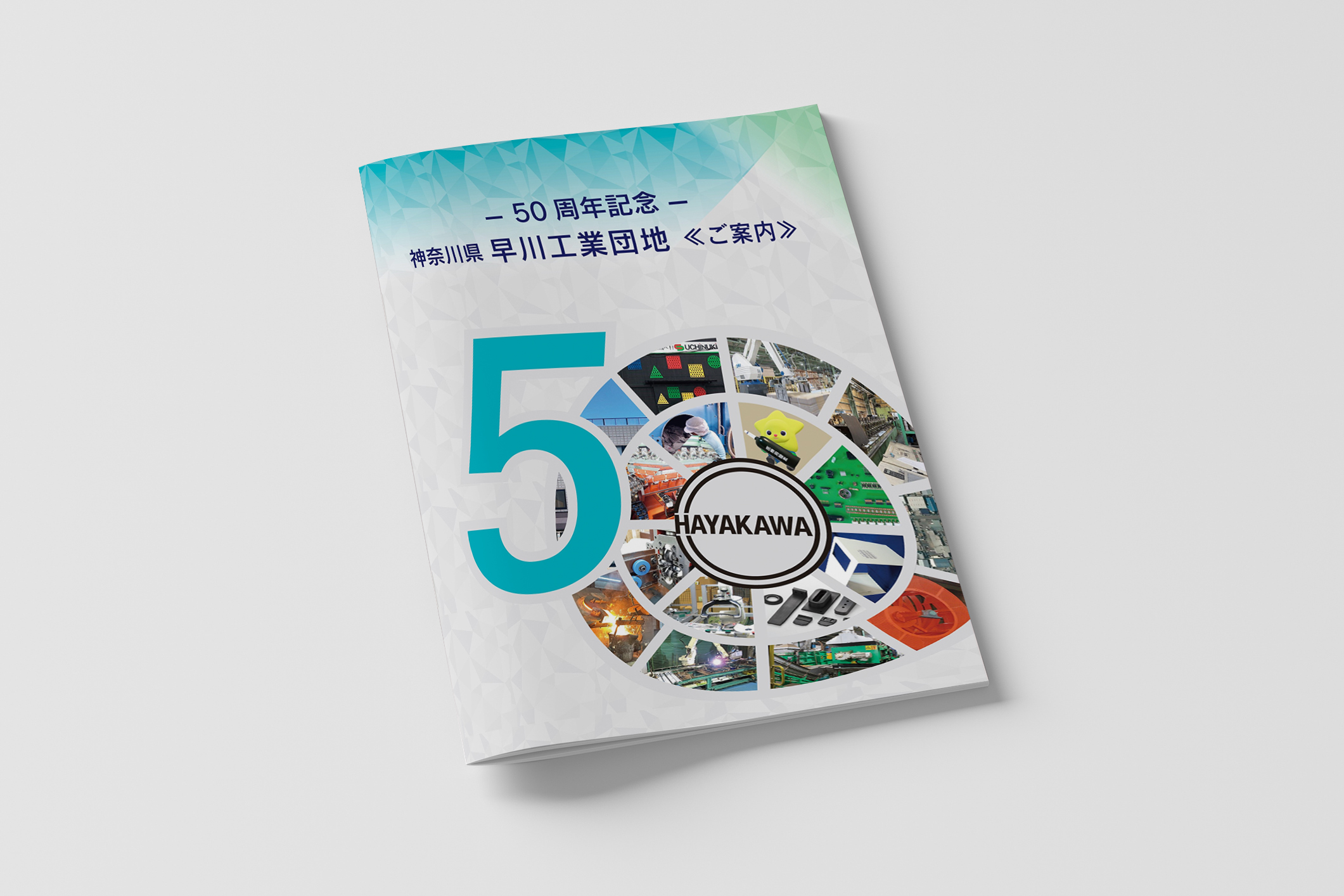
※当社の制作実績です。
しっかりとした冊子タイプのパンフレットを作りたいなら、8ページ以上の中綴じがベストです。
「中綴じ」とは、ホチキスのような金具で背を留める製本方法で、雑誌や小冊子のような仕上がりになります。
採用活動用で会社の文化や働き方を丁寧に紹介したり、営業ツールとして製品ごとの詳しい説明を載せたりと、複数の目的を1冊にまとめられるのが魅力です。 また、ページをめくって読む構造なので、情報を段階的に整理しやすく、長期保存にも適しています。
「見応えある構成で企業イメージを伝えたい」なら、中綴じ冊子を検討しましょう。
中綴じと無線綴じの違い
製本方法の代表格が「中綴じ」と「無線綴じ」です。中綴じはホチキス留め、無線綴じは接着剤で綴じる製本方法です。
中綴じは最大16〜20ページ程度までが目安で、軽量・低コストで気軽に使えるのが魅力。 一方、無線綴じは背表紙ができるため、本のような見た目となり、よりフォーマルで高級感のある印象を与えられます。
たとえば、カタログやIR資料などページ数が多い場合や、保存されやすい印刷物には無線綴じが向いています。逆に、持ち歩きやすく配布重視なら中綴じが適しています。
「読みやすさ」や「見た目の印象」、さらには「ページ数」に応じて製本方法を選ぶことが大切です。
タイプ別の制作パターンとそのメリット
| タイプ | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 中綴じパンフレット | 定番の冊子型 | 営業・ブランディング全般 |
| ポケットフォルダー+リーフレット | 差し替えができる | 複数製品や事業がある企業 |
| 中綴じ観音折り | フォーマル+機能性 | 官公庁、上場企業など |
| 変形・特殊加工 | 差別化と記憶に残る演出 | 新規開拓営業・展示会など |
中綴じパンフレット|定番の冊子型で営業・ブランディング全般に対応
中綴じパンフレットは、会社案内や営業ツールとして最もスタンダードな形です。
中心をホチキスで留めて冊子に仕上げるこの製本方法は、雑誌のようにパラパラと読み進めやすく、ページ構成も自由に設計できるため、伝えたい情報をバランスよく配置できます。
例えば、製品紹介や代表メッセージ、沿革、実績一覧などを段階的に並べれば、読み手が自然な流れで企業理解を深められる構成になります。 また、印刷費も比較的抑えやすく、小ロットから対応できる点もメリットです。
営業ツール・ブランディング冊子など、幅広い用途に対応できる汎用性の高さが中綴じの強みです。
ポケットフォルダー+リーフレット|差し替え可能で柔軟な構成が魅力
ポケットフォルダーとリーフレットの組み合わせは、製品や事業ごとの情報を柔軟に差し替えられる便利なスタイルです。
フォルダー本体には会社情報や理念などの共通項目を印刷し、ポケットに差し込むリーフレットには事業部ごとの製品情報などを個別に入れる構成です。
たとえば、商談相手の業種に応じて必要な情報だけを抜き出して渡せるため、相手に合わせたカスタマイズ性が高いのが特徴です。 定期的に製品内容が変わる業種や、複数の事業部を持つ企業に特に適しています。
常に最新の資料を届けたい企業には、このタイプの活用が非常に有効です。
中綴じ観音折り|フォーマル感と機能性を両立
中綴じ観音折りは、見開きページを大きく使える構成で、情報量とフォーマルな印象を両立できるのが特徴です。
観音折りとは、左右からページが開く折り方で、扉を開くような印象を与えます。これに中綴じを組み合わせることで、冊子形式の中に大胆なビジュアル展開が可能になります。
たとえば、1枚大きなビジュアルで世界観を伝えたあとに、詳細な実績や会社情報をページごとに整理して載せるなど、「魅せるページ」と「読ませるページ」のメリハリがつけやすいレイアウトです。
官公庁・上場企業・大学などのフォーマル資料におすすめの構成です。
変形サイズ・特殊加工|差別化と記憶に残る演出で新規開拓にも
形や加工でインパクトを与えたいなら、変形サイズや特殊加工を使ったパンフレットが効果的です。
通常のA4やB5ではなく、スクエア型や細長い縦型など独自の形状にすることで、手に取った瞬間に「おっ?」と思わせる仕掛けになります。
さらに、箔押しやエンボス(凹凸)、UVニスなどの特殊加工を加えると、高級感や tactile(触感) に訴える演出が可能です。 たとえば展示会で数十社の資料が配布される場面でも、形状と加工で印象に残るパンフレットは一歩抜きん出ます。
「他と違う」「記憶に残る」を目指したい新規営業やイベント向けにおすすめのスタイルです。
用紙・加工・印刷仕様の選び方
- マット紙・コート紙・上質紙の違いと使い分け
- PP加工、箔押し、エンボスなど表紙におすすめの演出
- 「高級感を出したい」「手触りを重視したい」など目的別に提案
マット紙・コート紙・上質紙の違いと使い分け
会社案内パンフレットの印象は「紙選び」で大きく変わります。
紙には主に「マット紙」「コート紙」「上質紙」の3種があり、それぞれ特性と向いている用途があります。
マット紙は光沢を抑えた落ち着いた風合いで、企業理念や代表メッセージなど“まじめな印象”を伝えるのに最適です。
一方、コート紙は表面がつるつるしていて写真の発色が良いため、製品カタログやビジュアル重視のデザインに向いています。
上質紙はナチュラルな質感で、ペンで書き込みができるため、申込書付きの資料や採用パンフレットにぴったりです。
例えるなら、マット紙は「上品な便箋」、コート紙は「カラフルな写真集」、上質紙は「コピー用紙に近い書き心地」です。
どの情報を誰にどう届けたいかによって、紙の種類を選ぶことが、印象を左右する大切なポイントです。
PP加工、箔押し、エンボスなど表紙におすすめの演出
表紙の仕上げにこだわると、会社案内全体の「格」がぐっと上がります。
そのために効果的なのが、「PP加工」「箔押し」「エンボス」といった表紙向けの特殊加工です。
PP加工とは、表面に薄いフィルムを貼る加工で、光沢感を出す「グロスPP」と、しっとり落ち着いた質感になる「マットPP」があります。
これにより、擦れや汚れにも強くなり、長く美しい状態を保てます。
箔押しは、金や銀の箔をロゴやタイトル部分に転写する加工で、視線を引きつける“高級感”が生まれます。
また、エンボス加工は紙に凹凸をつけ、ロゴなどに立体感をもたせる技術で、手触りでも印象を残せます。
たとえば、高級ホテルのパンフレットでは、箔押し×マットPPで上質さを演出していることが多いです。
特殊加工は視覚だけでなく“触覚”でもブランドの世界観を伝える、強力な表現手段です。
「高級感を出したい」「手触りを重視したい」など目的別に提案
パンフレットの仕様は「目的」によって選ぶのが正解です。
一見、デザインやレイアウトばかりが重視されがちですが、実は紙や加工の選定によって“伝わり方”が大きく変わります。
たとえば、「高級感を出したい」という目的があるなら、マットPP加工+箔押し+厚めのマット紙の組み合わせが有効です。
逆に「親しみやすさや柔らかさを出したい」場合は、上質紙+やや薄めの紙厚+手書き風フォントで温かみのある印象に仕上がります。
「実際に手に取ってもらえるパンフレットにしたい」なら、手触りや重さまで配慮して用紙を選ぶことが大切です。
印刷会社では、事前に紙サンプルや加工見本を見せてもらえることが多く、実物に触れながら決められる安心感があります。
仕様はデザインと同じくらい重要な「伝え方の武器」。目的に応じた最適解を一緒に見つけることが成功のカギです。
サイズで失敗しないために|よくある間違いとその対策
- 情報量とサイズが合っていない → ページ追加で調整
- 持ち運びに不向きな仕様 → 軽量・折り加工を選ぶ
- 見た目ばかり重視 → 読みやすさ・導線を忘れずに
報量とサイズが合っていない → ページ追加で調整
会社案内パンフレットでは「載せたい情報」と「サイズ・ページ数」が合っていないと、読みにくくなってしまうことがあります。
無理に1ページ内に詰め込もうとすると、文字が小さくなりすぎたり、レイアウトが窮屈で読者が離れてしまう原因になります。
例えば、会社の沿革・事業内容・採用情報など盛りだくさんにしたい場合、4P(二つ折り)では足りず、6Pや8Pへ増やすのが適切です。
ページ数が増えることで、情報を整理しながら見やすく配置でき、読者の理解度も高まります。
パンフレット制作は「名刺のように軽く伝えるのか」「企画書のように詳しく見せたいのか」で構成が変わります。
情報が多いのにサイズが小さい=詰め込みすぎ、が一番の失敗要因。
逆に、ページに余裕があれば、余白を活かしたデザインで「読みやすさ」「高級感」も演出できます。
まずは載せたい内容を整理し、それに合った構成へ調整することが成功の第一歩です。
持ち運びに不向きな仕様 → 軽量・折り加工を選ぶ
展示会や営業訪問などで配布する会社案内では「持ち運びやすさ」が重要です。
せっかく内容が良くても、大きすぎたり重かったりすると、持ち帰られずに置いて行かれる可能性があります。
その対策として有効なのが、軽量な紙やA5サイズ、折り加工(三つ折り・観音折り)などを活用する方法です。
たとえばA4サイズの3つ折りなら、封筒にも入りやすく、かつ内容もしっかり伝えられるというバランスが取れます。
「持ち運びに適したサイズ感=相手に配慮した設計」であることが、実は会社の印象アップにもつながります。
また、用紙も135kg前後の軽めのコート紙などを選ぶことで、バッグにもスッと入る仕上がりにできます。
読みやすさだけでなく、相手が“どう使うか・どう受け取るか”を考えてサイズ・仕様を決めることが大切です。
見た目ばかり重視 → 読みやすさ・導線を忘れずに
パンフレットでよくある失敗が「デザイン映え」だけを優先してしまい、肝心の情報が伝わりづらくなることです。
印象に残るビジュアルは確かに大切ですが、読み手が“迷わず理解できる”導線がなければ、本来の目的を果たせません。
たとえば、背景が派手すぎて文字が読みづらかったり、写真の配置に気を取られて順番がわからない…という事例も。
読みやすいパンフレットには、視線の流れ(Z型やF型)を意識した設計や、見出し・余白の使い方に工夫があります。
見た目重視のオシャレなデザインにする際も、「読者がどこから読んで、どこで理解するか」の流れ=導線設計は忘れてはいけません。
特に初めてパンフレットを作る方ほど、「自社が伝えたいこと」だけでなく「相手がどう受け取るか」を意識することで失敗を回避できます。
デザインと機能性のバランスが取れた構成こそが、“伝わる会社案内”への近道です。
まとめ|“伝わる会社案内”は、サイズと構成の設計から始まる
会社案内パンフレットは、企業の第一印象を左右する大切なツールです。
その中でも「サイズ」と「構成」は、見た目の印象だけでなく、情報の伝わり方や読みやすさに大きな影響を与えます。例えば、A4サイズは信頼感を与える王道の選択ですが、配布用にはA5や三つ折り仕様なども有効です。情報量に合わせたページ設計や、用途に応じた綴じ方の選定も重要です。
「誰に・何を・どう伝えるか」によって、最適な設計は大きく変わります。
採用向けなら共感を呼ぶ構成に、営業用なら実績とサービス訴求を重視するなど、目的に合わせた内容整理が欠かせません。
一度しっかりと設計された会社案内は、営業・採用・PRと幅広く活用できる“会社の資産”になります。
まずは自社の目的を整理し、実績豊富な制作パートナーに相談することで、納得のいくパンフレット制作が実現できます。
「思った通りの印刷に仕上がるか不安…」そんな方へ
「色味が思っていたのと違った…」「仕上がりの質感がチープだった…」
そんな印刷の失敗、もう繰り返さなくて大丈夫です。
ニチゲンでは、一般的な印刷よりも色が鮮やかで高精細な印刷技術に加え、デザインから印刷・製本までを社内で一貫対応。小部数でも、こだわりのある仕上がりを丁寧に実現します。まずは無料でご相談ください。
\仕上がりが不安な方はサンプルも提供/